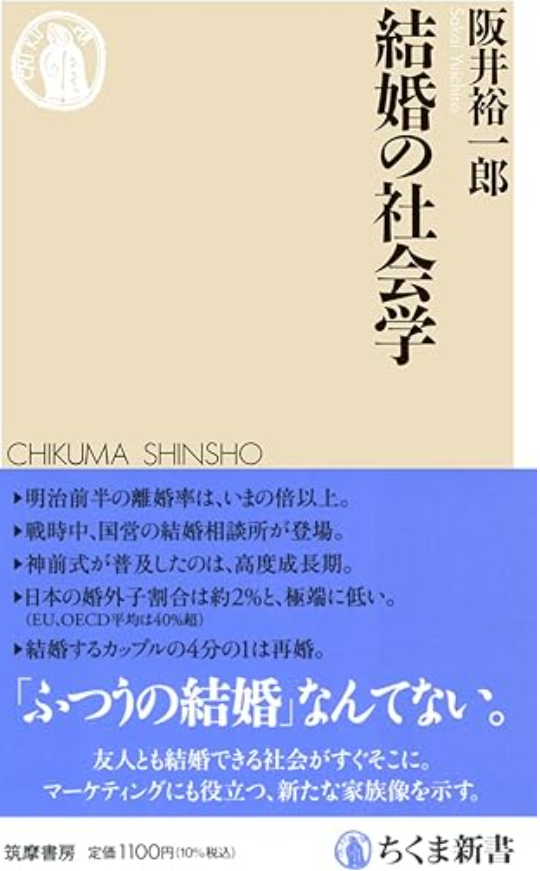
『結婚の社会学』を読了。結婚をテーマに「常識を疑うのが社会学」と述べた上で、様々な「常識」を揺さぶっていく展開がとても良い。例えば、「友達とは家族になれないのか?」「離婚の増加は悪いことなのか?」「国家はなぜ性的関係だけを優遇し特権化するのか?」など。
本書前半の歴史分析が面白かった。見合い結婚が明治以降に創られた伝統であった点、「よばい」や処女規範を含む庶民の性意識が、明治以前以後で変化した点、明治期以降に同性愛への眼差しが変化した点、19世紀末に日本が夫婦同姓原則を法制化した際に家や伝統を破壊に繋がるといった批判が起こった点、戦前期の日本が世界的に見ても養子大国であった点、戦後を代表するリベラル法学者の多くが事実婚を否定し法律婚主義を徹底するべきだと論じた点、恋愛結婚よりも見合い結婚の方が配偶者選択が本人中心的であった可能性がある点、1990年代の医者の仲人依頼料の相場が100万円だった事例(!)など。
欧米で出産・子育てと婚姻制度が分離したり、同棲が一般化している傾向にある。同時に、先進国の中で、低出生率国に共通するのは、家族主義が強固。一つ一つの事例に結婚とは何かと揺さぶられる。「コミットメント・フォビア」の話は、マッチングアプリの普及状況と併せて考えさせられた。
夫婦別姓への批判には特に手厳しく、夫婦の婚姻姓の決め方をくじ引きにしたら男女どちらから批判が起こるかなどユーモア炸裂。性愛と結婚の関係を考える上で、ファインマンやブレイクは参考になり、ケアの議論と地続きだと再確認できた。いずれの選択も支える制度設計の重要性が随所で指摘されていた。