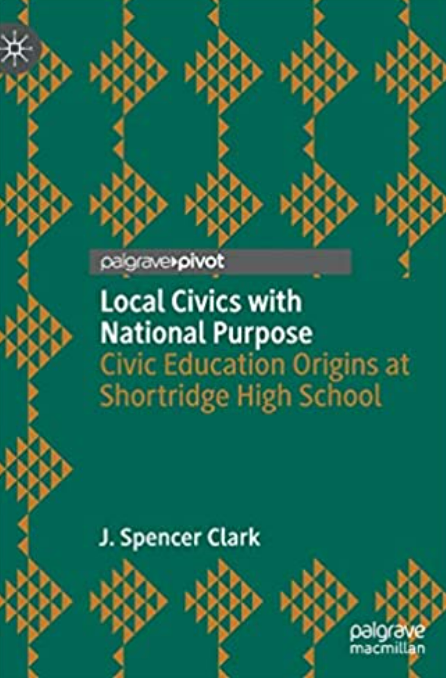
HES (History of Education Society)のHistorical Studies in Educationシリーズとして刊行されている本書。
米国社会科教育史としての面白さ、盛りだくさんです。
本書では、これまで、米国社会科成立の立役者(代表的人物)として捉えられてきたArthur W. Dunn(アーサー・W・ダン)がインディアナポリス時代に勤めたとされるショートリッジハイスクールの19世紀末~20世紀初頭の状況に焦点があてられ論じられています。
その上で、本書では、ダンの実践の意義の批判的再検討と、その先にある社会科成立史の再解釈を目指しています。
本書でダン以上に注目が当てられているのが、ダンがショートリッジハイスクールに着任する以前から長きにわたり同校で公民科の女性教師をしていたLaura Donnan(ラウラ・ドナン)の存在です。
ドナンの実践は、19世紀末時点で社会科成立期に匹敵する質の高い実践がされていて、なおかつ、アフリカ系アメリカ人の生徒がいる中で人種問題の論争問題を(歴史的限界はありつつも、公正志向に意識を向けて)議論するなど、当時から見るとかなり進歩的なものだったようです。
また、ドナン自身は、公民科以外にも、教科外活動としての生徒会や校内誌作成、地域でのソーシャルワークなどの社会改革運動にも非常に熱心で、社会教育の実践者としても、公民科教師としても、(社会改造主義的な意味で)一貫した女性だったと論じられています。
ちなみに、ダンがショートリッジハイスクールに勤務している数年間に、ドナンとダンは同僚でした。
そのようなドナンという補助線からダンを見たとき、
・ダンの提案、著作に大きなオリジナリティがあるわけではない点、
・ダンの提案の多くが、ドナンを含めた他の実践家の理論から得た知見が中心である点、
・そもそもダンはショートリッジハイスクールで公民科の専門ではなかったのであり、ダンが公民科の専門家として捉えられるようになるプロセスには非常に政治的(人間関係的)なつながりがあった点、
などが明らかにされていきます。
この描写の中で、
社会改造主義的な思想を持っていたドナンと、社会効率主義的な発想の強いダンという対比が強調されています。本書のダン解釈の背後には、Julie A. Reubenの研究の影響があることは強く感じられます。
例えば、ダン自身は、公民科実践を提案するわりに、地域への草の根の貢献活動に熱心に通っていたわけではない、という点などもドナンと対比して強調されたりもしています。
また、ドナンの実践から、ダンが(哲学的信念ではなく方法論的にのみだけ)影響を受けている点なども指摘されています。
一方で、ドナンの実践の意義を強調することで、社会科教育成立批判のようなリビジョニスト的解釈に陥らず、社会科教育のルーツとしての社会改造主義の意義なども示しながら論じられており、バランスの良さが際立っている印象です。
結果として、当初から腰を据えて社会改造的な実践を積み重ねていったドナンに全米的な注目が集まらず、そこまで蓄積的な実践のないダンが立役者のように出世していく背景に、著者はジェンダーの問題(女性教師の全米レベルへの提案力の弱さや、男性中心主義的な教育行政、都市改革の構造)を挙げています。
これらの主張、よく読むと、先行研究の前提を色々と覆すインパクトがとても大きくて、私自身、自分の研究について考えさせられました。
(ダン解釈がそこまで言えるのか、やや疑問点もありはしますが。)
また、本書を読んでいて一番印象的なのは、史料についてです。
本書で出てくる史料の多くは、ショートリッジハイスクールの学校誌であったり、インディアナポリス市の新聞記事などです。
私の知る範囲ですが、こういった学校雑誌や新聞記事を網羅的に使って論じる米国社会科教育史の研究は、非常に少ないような気がしています。
そういう意味でも、2000年代の米国社会科教育史の動向として、より実証的に、よりテーマや対象を焦点化して、より緻密な論証をしておこうとする傾向を感じます。
(インディアナポリスには、10年以上前に私も行ったことがあるのですが、このような史料が眠っているとはつゆしらず、私は全く別の史料などを探しておりました。)
特定の学校に焦点を当てているという意味ではマニアックな研究にも見えますが、その焦点化された視点の射程は非常に広く、大変刺激的に思いました。
同時に、日本人が米国社会科教育史の研究をする意味って何なのだろうと、改めて考える機会となりました。
勉強になりました。