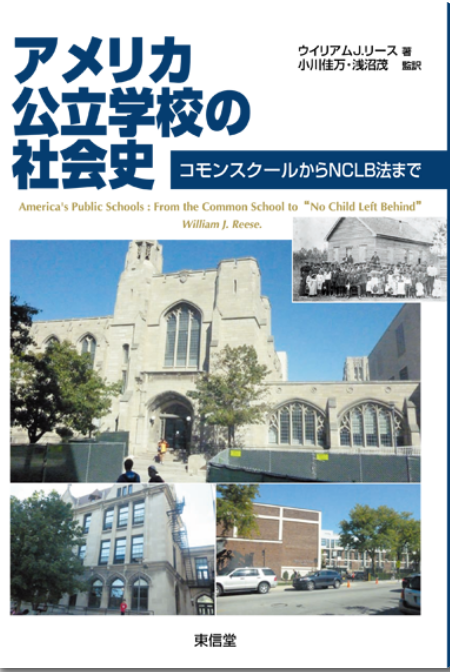
約200年のアメリカの公立学校の歴史を描いた本です。
これまでつまみ読みばかりで、通読するのは実は初めて。
450ページ以上ある本ですが、目次は以下の通りです。
序 論
第1章 コモンスクールの起源
第2章 南北戦争後のアメリカとコモンスクール
第3章 「新教育」
第4章 民主主義、効率、学校の拡大
第5章 差異の民主主義
第6章 大衆のカレッジ
第7章 高まる期待と水準
第8章 伝統の保護者
第9章 ハイスクールの運命
エピローグ
『アメリカ公立学校の社会史』解説
本書の最初にはこう書かれています。
本書で、私は密接に関連する二つの現象に注目する。一つは19世紀初頭以来、学校を通して社会を変革しようとする多くの市民による絶え間のない試み、もう一つは学校組織、カリキュラム、教育実践、教育目標全体を変革するための学校内での論争である。
p.5.
この言葉にもある通り、本書が対象とする論点は多岐に及びます。学校と社会のかかわりや、社会に翻弄される学校、社会を変えようとする学校、そして、具体的な組織、カリキュラム、授業など、様々です。
読んでみると、時代が行き来したり、様々な事例がエピソード的に書かれる場面もあったりして、文章表現も含めて必ずしも読みやすいわけではないのですが、
ロングスパンで学校教育を捉えることの重要性を実感できますし、教育史研究のアプローチの射程の広さを感じさせてくれる本のように思います。
いくつか印象に残った箇所をメモしておきます。
一点目
学校教育に求められる役割が、200年間を通じて、態度や人格的なものと学力的なものの両方であった点です。その時々で振り子のように動いていますが。
ハイスクールも大規模な社会変動の中で、専門教員が一般に対立するものと考える二つの目標、すなわちハイスクールの民主化を欲する人々と、ハイスクールをアカデミックな卓越性の中心として保護しようとする人々との緊張状態であった。
p.8.
世論調査は国家テストと高いスタンダードへの広範な支持を示すかもしれないが、学校から多くの社会的義務を取り除いて勉強に集中させたいと思うアメリカ人はほとんどいない。ほぼ2世紀の間、社会正義、人間の平等、個人の進歩のための運動のほとんどすべては、一部の公立学校で行われてきた。伝統的な科目、価値観、道徳の維持のための大衆運動もそうである。
p.450.
実際、公立学校の誕生期はキリスト教の宗教的理念とも密接にかかわるですが、以下の「敬虔さなしに学習することは危険である」という表現は、学校教育の持つ役割の二重性を感じさせてくれる内容でした。
公立学校の活動家と教育者は2,3の中核的な信条から決して外れることがなかった。それらは、最も健全な倫理がキリスト教から、特にプロテスタント主義からくること、敬虔さなしに学習することは危険であること、そして学校が心の訓練に関与する際は、優れて人格形成に焦点化すべきであるということである。
p.47.
二点目
本書が、レトリックや表舞台で語られる理論や改革の一方で、変わらない現実についても細かに論じている点です。
特に勉強になったのは、「学校は変わらない」という安易な悲観論ではなく、(時にはポジティブな意味も含みつつ)変わらない理由や、学校側の抵抗について論じられているのが印象に残ります。
新教育の支持者は、改革の種を育てることに失敗してしまったと知った。歌うたいドリル、3Rsの拡大版、質疑応答教授法、教科書の頻繁な利用は大部分の学校で残ったのである。
p.154.
将来の教員と新進アドミニストレーターのための教科書は、標準テストの価値を強調した。しかし、多くの学区ではテストを無制限に購入できるわけではなかった。また、多くのアドミニストレーターは結果を解釈するために奮闘し、教員は科学的な慧眼が足りないと批判されながらも古い方法で教え、学級を編成していた。さらに、地域では心理学者やガイダンス・カウンセラーやテストに精通した専門家を十分雇っているいるようにもみえなかった。いくつかの都市では、教育学的に多くの子どもたちを振り分けるのに役立つような独自の調査部局を1920年までに設立してはいたが、多くのアドミニストレーターは、学級実践を劇的に変えるほどの原資や人材を確保できなかった。さらに、能力別グループ編成は、次第に学年制の規準となる一方、教育科学やテストが約束した新たに改良された教授法を生み出していたわけでは決してなかった。
p.222.
小規模校は、多くの親同様、アカデミック・コースを支持する保守的な教員を多く有していた。これらの授業をとりやめることは、たとえ大多数の生徒が卒業証書を受け取ることがないとしても、学校の認証を失う危険があり、地元の校長にとっては名案ではなかった。1940年に、ある教育者が指摘したように、典型的なハイスクールは小規模であり、多くの専門家たちによる10年間にわたるアドバイスにもかかわらず、その質はどうあれ「正真正銘のアカデミックコース」を提供していた。
p.273.
三点目
教師の姿が各所で描かれていることです。授業をする教師というよりは、教師がどのように働いたり、どんな特徴だったりしたのか、という話が多いですが、各時代の学校の位置づけを理解するうえで、大変有益な情報となっています。
1830年には白人の3分の1が10歳未満であった。南北戦争以前は、家の外にはまともな就職先がほとんどなかったため、北部の都市で、のちの数十年には地方でも、女性は次々と小学校教員となっていった。
p.38.
田舎の教師が都市に魅力を感じたのは、高い給料や学年制を含めた改革の進行と質の高い生活への評判のためであった。1895年全米教育協会による田舎の教育に関する報告によれば、大部分の師範学校の卒業生は、進歩的な教授法を研究し、情報を集め、都市に押し寄せている。つまりヒエラルキーと秩序が制度の柱となっていたのである。
p.153 .
ほとんどのハイスクールの生徒は、南北戦争後まで上級学校へ進学する機会のなかった女性で、彼女たちはコモンスクールの教員になっていった。
p.241.
大多数のハイスクールは、わずかな教員と数十人の生徒だけの非常に小さな学校で、選択科目や職業科目を提供することができなかった。カレッジへの進学を熱望する生徒の数は少数といわれ社会的に影響力があることから、学習指導要領に沿うことを認定要件とし、したがって学習指導要領はカレッジ向けでも非カレッジ向けでもカリキュラムの中核となった。
p.243.
ハイスクールの教員はまた、小規模なクラスで教鞭をとり、1930年代にその差が縮小し始めるまでは、小学校の教員よりも高い給料が支払われ、高い社会地位を享受していた。
p.271.
新人教員は、ゲットー(スラム街)の学校に配置され、彼らがそこで生き残り、もしくは成長することができたならば、彼らは「より良い」ポストへ異動し、昇進することができた。
p.313.
公的に分離された学校が姿を消したとたんに、多くの黒人教員とアドミニストレーターは仕事を失ったが、初等・中等学校の黒人の教員の数は、1940年から1970年の間に、6万7580人から22万7000人へと劇的に増加した。
p.328.
20世紀の半ば、小学校の教員の大多数が女性であり、たいていの教員のカレッジでアカデミックな教科を専攻していなかった。1957年の全米教育協会の研究によれば、小学校の教員のうち、約3分の1がカレッジを卒業していなかった。また、卒業した者のほとんどは教育学の学位を取得したが、彼らは『タイム』や他の全米をカバーするような雑誌の中で、キャンパスにおいて最も弱い学生であると風刺された。およそ2年間のリベラル・アーツ課程の後、教員志願者は様々な教育学の授業を履修し、教育実習を行い、州の免許状を申請した。教育学の教授陣が学校について教えたことは、彼らが生徒として成功を感じた組織に対する非現実的な、あるいは過度な批評であり、年配の師範学校緒の卒業性が彼らに昔話を語るようなものだった。彼らのと別にある理想に応えられるものはわずかであった。しかし、学位は次第に、将来の採用への必要条件、不可欠なハードルとなっていった。
p.343.
四点目
アメリカの地域の多様性や、都市と田舎の違い、南部と北部の状況の違いなど、各時代における「場所」の違いによる状況の違いが浮き彫りになっている点です。
一つの論点は田舎の教育になります。
都市が発展したにもかかわらず、19世紀後半では大半の人々は、主要都市以外の地域で生活しており、彼らの子どもたちは小規模で簡素な学校に通っていた。それらは、多くが学年制ではなく、統一されたカリキュラムを欠き、教員は通常一生の仕事ではなく、短期間のものとして働いていた。州の教育集会や全米教育協会での講演者は、田舎の学校の欠点を嘆いた。
p.89.
南北戦争以前のように、田舎に住む子供はどこでも、同じような学校に通った。それらの学校は、未だに素人が管理し、主財源は地方税であった。都市と比較すると、カリキュラムは統一されておらず、最低限の内容のみ教えられて、無学年制で、教員はほとんど管理されず、生徒の通学には天候、農場の仕事、親の関心、そのほかの個人的な要因が影響した。
p.93.
南部・北部の違いも詳述されています。
社会の変化は、南北戦争後のアメリカの風景とコモンスクールを劇的に変化させた。ナショナリズムの台頭や都市の産業化、統合された経済にもかかわらず、地域間格差は長い間アメリカ人の生活を特徴づけた。北部の人々はコモンスクールの美徳を称賛し、国内の人種問題を軽視し続ける一方で、南部を文化的・教育的僻地と呼んでいた。たとえ進歩が見られたとしても、また小規模な経済基盤において学校関連に割く予算が大きくても、南部は北部より教育に関して遅れをとっていた。平均的な南部の子どもは、北部の子どもより在籍日数においても在籍年数においても少なく、教育発展を遂げたにもかかわらず、アフリカ系アメリカ人の学校への投稿は多くの場合不十分で、皆無の場合もあった。
pp.103-104.
1960年代後半に南部の学区は、連邦政府の蛇口から流れ出る様々な資金を失うだけではなく、高くつく裁判闘争に負けるであろうことに気がついた。人種差別撤廃への誘因は増大した。・・・(中略)・・・特にミシシッピ州のような貧しい州は、タイトルⅠから学校給食に至るまで、近代学校の外観を整った状態で維持するためには、連邦政府からの資金援助に頼っていた。皮肉にも、ブラックパワーの活動家が学校統合を攻撃したように、連邦政府は、実際にそれを実現させるために強力な圧力をかけた。
p.328.
また戦後アメリカの学校の多様性も紹介されています。
戦後のアメリカの小学校について概括することは、その大きさや多様性、複雑さによって困難であった。1949年~50年度では、アメリカには8万3718の学区がアリ、1900万人もの生徒がハイスクール以下の何万という学校に在籍した。急速に減少してはいたものの、田舎には教員が1人の学校が6000校近く残っていた。30年後、黒人座別は法的に廃止され、在籍者数は2800万人を越えた。単学級の学校は1000校以下となった。そうした学校に、多様な学習障害を抱えた子供たちが新たに在籍するようになり、時には普通学級の主流となった。・・・(中略)・・・教育に関する連邦政府の役割は、第二次大戦後は劇的に増大したが、アメリカ人は州や地方の力を弱めることについては反対し続けた。その結果、独立した省レベルの教育省は1979年まで設立されなかった。
p.338.
1950年代のアメリカの小学校の多様性をとらえることができるような単一のイメージはない。つまり、財源不足で蒸し暑い学校で奮闘するテキサス州や南西部のメキシコ系アメリカ人もいれば、嵐の日にはすきま風が鳴るような残りものでできた丸太小屋で学ぶ黒人差別制度の残る南部に住むアフリカ系アメリカ人もいれば、素晴らしい図書館や映写用のスライド、映写機、さらには白黒のテレビまで備え付けられたコンクリートやガラスの教会で学ぶ白人の中産階級もいたのである。
p.340.
とりわけ20世紀半ば以降の都市と郊外の対比状況も地域差を示す一例です。
北部の都市における人種統合の見込みは、さらなる経済の困窮が人種間の対立を悪化させ、白人たちが都市から去ったため、今まで以上に困難になった。
p.331.
郊外への移動は、彼らの子どもたちが全てのものに対して有利な立場に立つことを確実にする一つの方法であった。しかし、才能のある子どもを対象とするプログラム(そしてハイスクールでの新たなAPプログラム)は、中・上流階級の白人(そして貧困からそこにたどり着いた黒人)に最も質の高い教育へのより良いアクセスを保障した。あらゆるジェファーソニアンが全てのクラスに如何に才能が内在しているかを述べたにもかかわらず、貧困層がギフテッド・プログラムや新たなカリキュラム・プロジェクトの利益を得られる見込みはなかった。
p.377.
五点目
本書がNCLB法までの歴史を描いていることもあり、テスト政策や評価・測定の問題については、関連する情報がちりばめられています。
それによって、アメリカにおいて、個人差やテストに類する問題、試みが古くからあったこと、NCLB法の話は、突如生まれたというよりも、歴史的に作り上げられてきた側面があることが示されているようにも思います。現代を相対化する意味でも、重要な役割を果たしています。
南北戦争前の学校の大多数は、生徒の進歩を判断するために多様な方法を利用していた。しかしながら、大多数の生徒たちは、教材を暗記し、教員の満足のためにそれを暗唱し、より難しい教材や新しい教材に進んでいった。口頭試験は、大部分の学校、特にい何万という田舎の教室で教員の主観的判断による中心的な評価方法であった。教員は、単語の綴り競争や、保護者や地域の重要人物の前で、学校のアカデミックで優れた能力を強調するための学校博覧会を支持した。教員は公開試験の前に生徒に質問したが、その練習は嘲笑の対象となったにもかかわらず、ほとんど廃止されなかった。南北戦争の後、工場が生産性を測るための方法を採用するようになると、特に都市の学校でも客観的な生徒の成果の測定方法を考案し始めた。1870.80年代までに個人の進度を判断し、次の学年に進級することを支援するための、毎日、毎週、毎月実施される多様な記述・口述試験を年の学校は利用した。またハイスクールの入学試験は一般的になった。
p.149.
19世紀の教育者たちは、子どもたちの学習能力には差があることを悟っていた。多くの子どもが通う教室一つだけの学校では、一人ひとりが教科書を自分のやり方でこなしており、都市だけが統一されたカリキュラムを採用し同年齢で編成される学年の教室をもっていた。したがって、ほとんどの教室の生徒たちが、自分たちの教科書と学習指導要領(実質的に同じものであった)をその能力とやる気に応じてマスターしていった。南北戦争前後の改革者たちは学年制学級を賛同していたが、戦後には次第に批判が高まったのであった。自動中心主義を主張する教育者たちは、過当競争のテストや成績至上主義での高等教育志向を嘆き、それらが個人の表現力を封じ、個人への注意をそらしてきたと信じていた。批評家たちは、学校は機械のために子どもたちを犠牲にし、矯正ベッドに子どもたちを縛りつけ、共通カリキュラムの祭壇に子どもたちをささげているとたとえていた。進歩主義時代の子どもたちは、勉強に奮闘していたが、教科が多くてうまくいかないことが多く、落第の辱めに耐えながら、結局未熟なまま学校を退学していくことが多かったのである。
pp.204-205.
経済不安と学校に対する不満は、レーガン政権時における教育改革への直接的な背景となった。しかし、学校と経済的性向の関係性、世論調査において明らかとなったスタンダードへの関心は、第二次世界大戦後のアメリカを大きく変化させた歴史的な発展を映し出していた。
p.288.
発達心理学者のロバート・ハヴィガーストによる1960年代のシカゴの研究は、ハイスクールの教員が、成績に関係なく審級させることが一般的になり、学校ごとに実践が異なっていることに特に悩まされていることを明らかにした。州の政策がなくとも、多くの生徒を合格させるよう校長からの圧力は増大していた。
p.355.
新しいテスト運動は多くの役割を担っている。最初のカーネギー財団の資金提供と当時の議会予算で、全米学力調査が1969年に始まった。「国家の家計簿」と呼ばれたそれは、定期的に様々な科目で生徒の到達度をテストしたが、個々の生徒や学校ごとの平均点を報告しなかったため、最低限の能力の測定や、他の学業テスト程には教育者の間で論争の的にはならなかった。全米学力調査は、数十年前に進歩主義教育協会に支援された有名な8年研究(1933-1941)の研究チームのリーダーを務めた、熟練した教育研究者であるラルフ・タイラーの研究に多くを負っていた(専門雑誌は満足そうにこの研究を引用し、形式陶冶概念のような伝統的なカリキュラムが、どんな科学的基礎も欠いていることをこの研究が証明していると述べた)。
p.412.
新しい連邦法が通過するずっと以前から、ほとんどの州が、以前多くの学区で定期的に用いられていたIQテスト、学力テストや他の統計的手法を組み合わせて、自前のテストプログラムを確立していた。他国では同様の批判を受けているが、アメリカの生徒は世界のどの生徒よりもスタンダード・テストを受けており、これからもさらに数多く受けようとしているのである。
p.445.
以上です。
正直、多岐にわたる論点が盛り込まれた本で、たぶん次回読んだときは印象が変わりそうなのです。
今の自分にとっても、多くの収穫がある本でした。