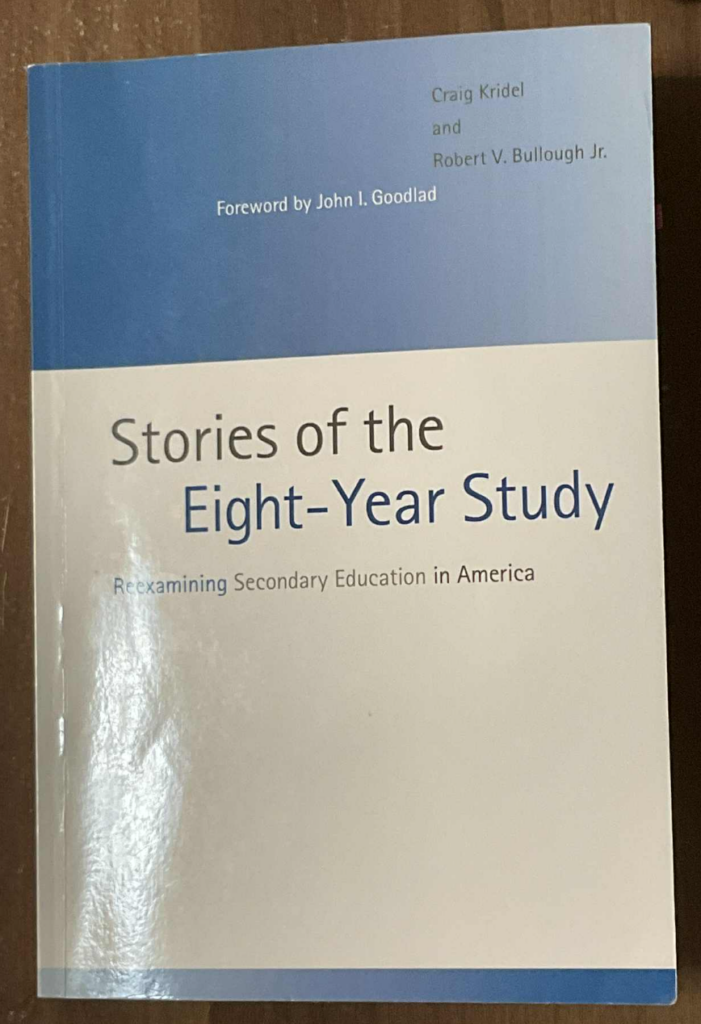
米国教育史においても著名な8年研究の再解釈を行った本です。8年研究は、歴代の先行研究でも著名であるものの、一面的なイメージで語られている部分が多いとされています。
8年研究は、一般的には、1930年代に主に実施され、進歩主義的なカリキュラムを受講したハイスクールの卒業生とそうでないカリキュラムを受講したハイスクール卒業生の卒業後(大学時含む)の調査を行ったとされる研究、と認識されているように思います。全米の合計30校のハイスクールが長期にわたって協力した大規模なプロジェクトでもありました。
ただ、本書から見ると、その結果やプロセスが誤った形(おそらく研究・調査の理念や趣旨とずれて)で世の中に理解されている点や、その後の進歩主義教育批判の言説の中で消費されてしまった側面があるようです。私が読んだ理解では、両者(進歩主義教育を受けた卒業生orそうでない卒業生)を「比較」することに目的はなかったのに、比較することにばかりメディアや社会的な注目が集まってしまった、ということかと思います。ここら辺は私も例にもれず誤解していた感じがあり、非常に勉強になります。
読んでいて、印象の残った点をいくつか紹介します。
一点目は、8年研究と研究を支援する財団との関係についてです。
当初、8年研究を支援していたのはカーネギー財団でしたが、カーネギー財団にとっては、8年研究のAikin委員会が主張する理念が現実的でないと捉えていて、カーネギー財団としては、開発、実験中のテストプログラムを実施したかった。しかし、8年委員会の理念を重視するAikin委員メンバーやそれを支持する実践家の考えとは異なる。ここで内部で対立が起こり、結果として、カーネギー財団は8年研究と距離をとるようになり、その後の支援団体はGEB(General Educational Board )に代わっていきます(pp.55-59.)。このプロセスが結構面白く、財政支援をしてくれる団体と委員会の理念のズレが生み出す対立の様子がドラマチックですらありました。
二点目は、生徒の実態把握をめざす観察や評価研究が発展していく様子についてです。
上記のカーネギー財団が促したのは標準テスト的なものでしたが、8年研究の評価研究自体は、より生徒の実態を把握する方法の開発へと向かっていきます。
その過程で例えば、参加校の教師がホームルームやランチタイムで生徒と関わるなど、いわゆるガイダンス機能的な役割を担う機会が増えていきました。これらの役割変化は、生徒の状況をより詳細に把握するための変化でもあったのですが、ケリファー委員会やザカリ―委員会などが中心となりながら、生徒の記録を基にしたケーススタディを蓄積し、それを教師向けのワークショップへと還元していく、教師教育的なプロセスがとても刺激的でした。量的なデータではなく、事例研究や個人史的なアプローチとして、生徒理解や学習評価をしようとしている様子が、主に「第4章 ガイダンス、人間関係、青年期研究」に書かれています。
三点目は、八年研究があくまでも実験校の自主性を重視している点です。
8年研究への参加校は8年研究の理念にある程度共感しつつも、その実態は非常にバラバラであったことが指摘されています。実際、学校間の格差が大きく、報告書の成果報告の全学校の平均点などにメディアの注目が集まったことで、8年研究が誤解されてしまったともいわれます(p.23.)。一方で、逆に言えば、8年研究の実験学校はかなり多様なカリキュラム開発をしていたようです。それぞれの学校が例えば教科委員会が提案した4領域のカテゴリー「個人的生活」「即時的な個人的社会的な諸関係」「社会的・市民的関係」「経済的な関係」を参考にはしています。ただ、8年研究の実験校を分析したロバート・例の調査によれば、参加校のコアカリキュラムの特徴についても、文化史段階的なコア、広範囲デザインコア、生徒の興味関心コアなど、異なるタイプのカリキュラムが見られたようです(pp.146-147.)。本書では、特にオハイオ州立大学付属学校でのコアカリキュラム導入過程の分析が詳述されていまsが、教師も親もその効果に懐疑的で、生徒も動揺していたところから、徐々にカリキュラムを改革していった過程がとてもリアルに思えました。トップダウンに理論を実践しようとしたわけではないという点が、進歩主義教育的なプラグマティックさを再認識できたりもしました。
その他、8年研究のカリキュラム改革を各校で進める中で、学校の哲学であったり、カリキュラムの社会的目的のようなものの重要性が認識されていく(逆に言えば、最初から哲学をどっしりと据えていたわけではない)プロセス(p.170-180.)も興味深かったです。