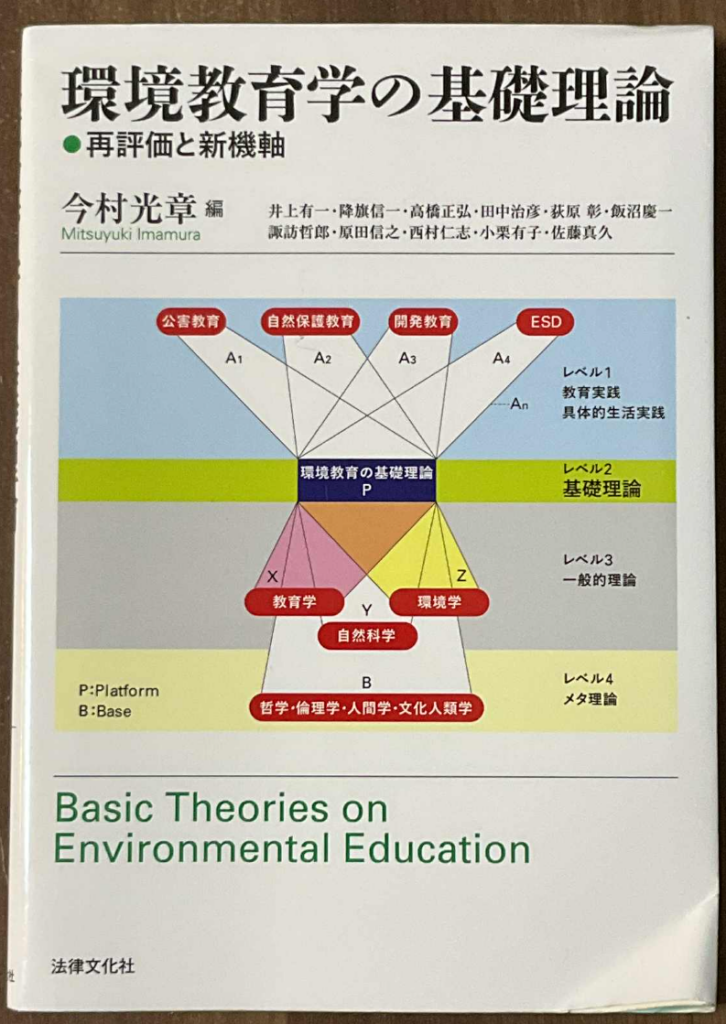
全体を通して、環境教育の学理論や原理論、学問論を問い直そうとする意識が随所に現われており、この分野の研究者・実践者のアイデンティティや葛藤を感じられる本になっている気がする。
とりわけ印象に残ったのは、環境教育の持つ政治性や運動性をどう捉えるかという点であった。10章にこんな文章があった。
「かつて公害の発生地域では、その発生の原因や被害状況、防止や解決の方法について学ぶと共に、子どもたちの健康を守る教育活動として「公害教育」が取り組まれた。ところがこうした活動は「偏向・イデオロギー教育」であるというレッテルも貼られる。筆者自身、学校教員の環境教育研修の講師を務めた際に某市の教育委員会の主事から「子どもたちへの環境教育はどんどんおやりになっていただいていいのですが、『環境問題教育』は困りますよ。」と釘を刺されてことがある。」(p.149.)
まさに、本来、環境を考えることは、様々に発展し得ると思うし、環境教育と環境問題教育だった、線が引けるものでもなければ、両方やってこその生きた学びということだって言いうるだろう。ただ、この引用部の話は、11章で書かれている、「地域が環境教育と置き換わってしまう」(p.167.)とも関連しているように思えるし、公害教育から、単純に脱政治化された環境教育にならないような工夫をどうしていくか、併せて、社会運動性や規範性をどの程度担保していくか、という点を考えさせられる。やはり、「地域」を掘り下げていくことは、環境教育の原点の一つでもあり、同時にとても(よい意味で)ラディカルでもあるのだと再認識できた。
その他、開発教育における、「開発を進めるべきか?」を問い直すための開発論がいくつも紹介されている。(「優しい資本主義」「新自由主義」「オルタナティブな開発」「脱開発論」など。p.79.)。
ドイツの動向が紹介されるケースが多く、もう少し掘り下げて専門書で読みたい気持ちにかられる。「第9章 ドイツにおける環境教育の光と影」では、1980-90年代のドイツ環境教育を「教化・訓育型の環境教育」「「エコ教育学」のタイプ」「自然体験はの環境学習」の三つに整理している。さらにその後の環境教育の特徴を整理する際に紹介されている「「シュテルン統合図」というものが分かりやすかった。環境教育論が6つのコンセプトが内在しているとして、「全体的に自然と交わること」「文化的側面への方向付け」「政治教育」「環境コミュニケーション」「エコ倫理の向上」「地域での行動」などの軸で整理している(pp.136-137.) 。
「ソーシャル・イノベーション」の文脈で語っている10章が、NPO法人グリーンウッド自然体験教育センターの事例を含め、印象に残った。