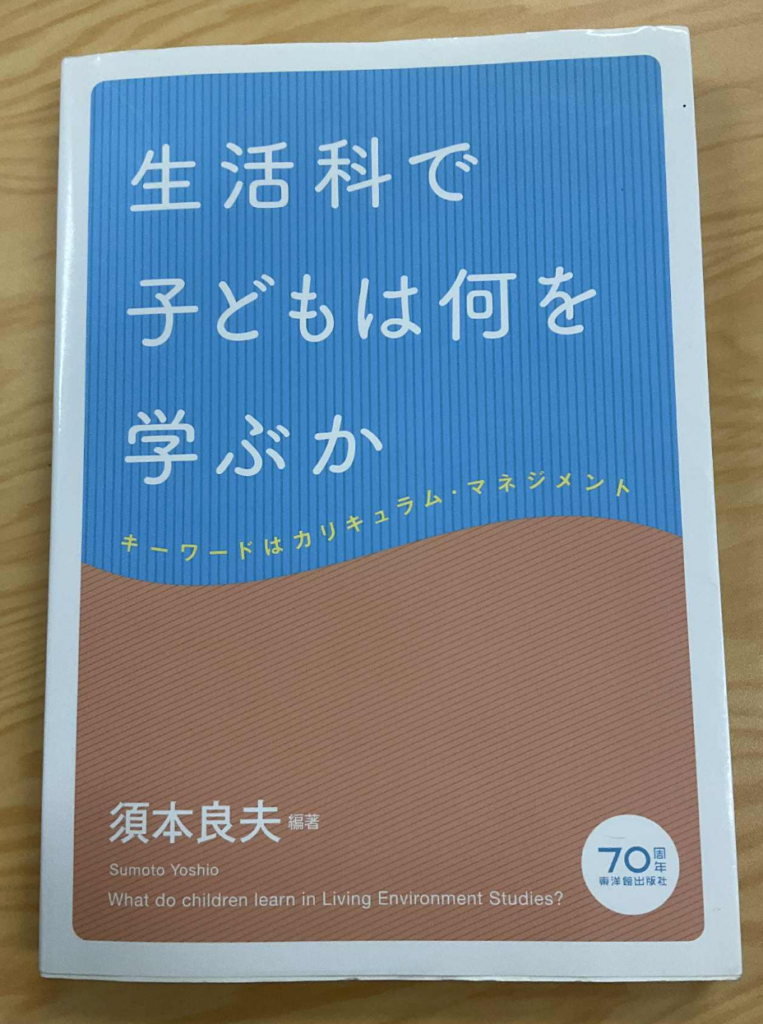
生活科にとっての「気づき」の重要性を軸に、本全体が構成されているように読めた。本書では、生活科と他教科との決定的な違いとして、①自分自身への気づきを大切な学習活動としていること②具体的な活動や体験を通して行われる学習方法(p.85.)などを挙げているが、印象的なのは、本人の「気づき」自体が、外から見ているだけでは見えてこない点であった。教師が「気づき」を得るためには、もちろん児童理解や児童への共感がベースになってくるのだが、子どもなりの表現の背景にあるこどもの思いを引き出す方法として、対話の重要性が挙げられていた。(p.88.)。また、子どもたちを適切に見取るためには、「黙って見ているだけでは不十分」とし、子どもに「声をかけてみること」の重要性を指摘している(pp.92-93.)。ここら辺の話は低学年の児童の発達のばらつきや表現のスキルに限界があることなども関係してくると思われる。だからこそ、児童がどういった気持ち意見を持っているのか、教員側がどう・どこまで関わっていけるのかという点が鍵になるように思える。途中で、子どもの話し合い、活動に教師が介入しすぎない点が述べられており、「教師が勝手に「割れたものがダメだよね」と言ったりしては、教師に逆らえないという、権威に迎合する集団を育ててしまいかねない。」(p.78.)ともあった。時間的余裕を持ちながら児童同士の話し合いの結果として、何らかの回答にたどり着くプロセスの価値を重視する。これは話し合いの結論が読み切れないことを含め、教員側に柔軟な対応策が求められる。本書では、それらの「気づき」を対話的に「発見」していく、(結果ではなく)プロセスこその意味があることを、複数の理論的視座や実践例の紹介に基づいて論じていた。