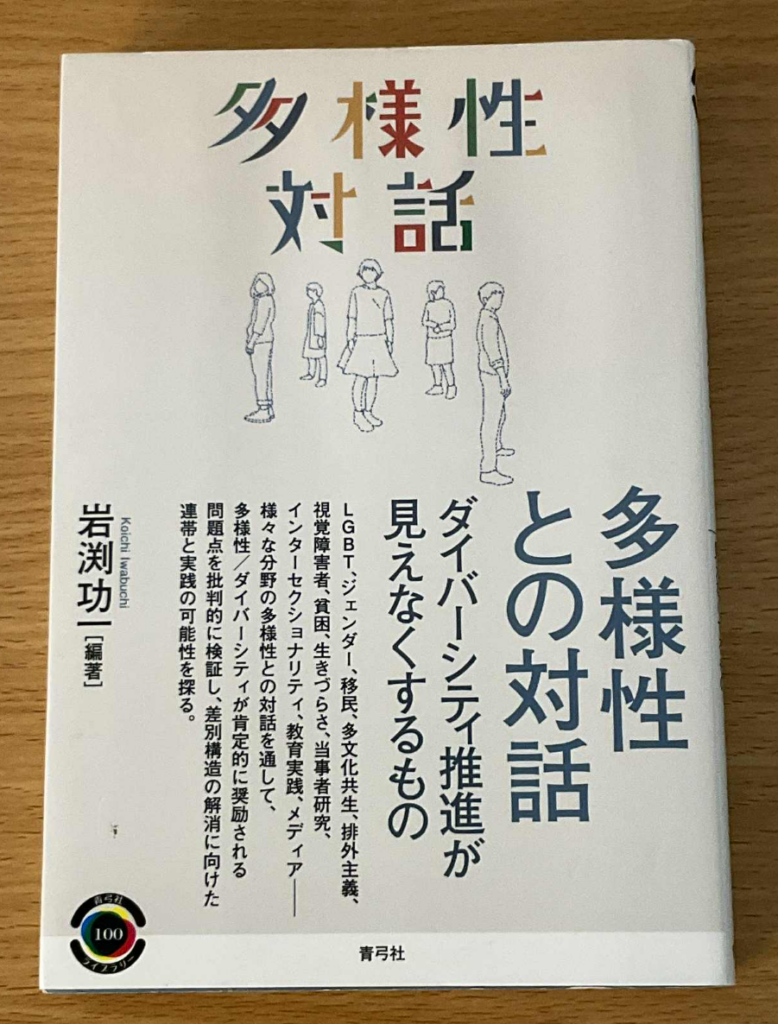
行政や民間の多様性/ダイバーシティの奨励・推進のあり方に対する、なかなか言語化しづらい違和感。もちろん、多様性の尊重される社会になることには心から賛同したいが、何か予定調和のように様々な変化が進んでいく時代の流れに感じる違和感。これを感じている人は一定数いると思う。本書は、多文化主義の視点に立ったうえで、その違和感を鮮やかに論じている本だった。LGBTマーケティングの話で、LGBTという「イメージを商品化すること」によって企業がブランディングをしているという話(p.49.)は、時として感じる広告情報の違和感を言語化してくれる感じもある。同時に、その影響力の大きさや戦略の巧みさの陰で、「利用価値を見出さない日がいつかくれば」廃棄される運命にないか(p.53.)という指摘はまさにそうで、見た目の良さ・巧みさに隠れがちな人権擁護の土台の重要性を再認識させられた。「誰にとっての多文化共生か」(p,75.)という問いも非常にクリアで、自治体での多文化共生施策が、例えば、難民(申請者)や技能実習生、短期での移民などを想定しているのかを批判的に検討している。生活保護の議論では、扶養義務に関わる家族主義的な価値観を援用すると、日本人/外国人の境界が強化される(p.102)ともされる。アイデンティティポリティクスのようになりがちな構図の中で、5章の「<名前のない生きづらさ><名前のある生きづらさ>」(p.131.)や、6章の「『同じ女性』ではないことの希望」(p.145.)の話は、問題の複雑さをイメージするのにとても良い位置に見えた。官製のダイバーシティの言葉への違和感を紐解くために良書だと感じた。