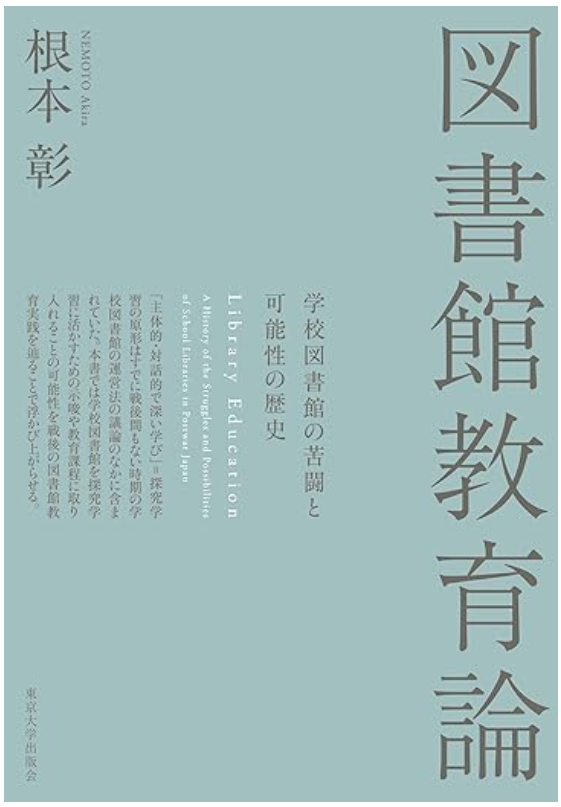
『図書館教育論』を読了。日本の学校図書館研究の抱えるジレンマや、複数の論点が歴史的に浮かび上がる本だった。学校図書館法が1953年に制定され、司書教諭を「当面の間、置かないことができる」とされたことから始まる苦難の歴史。その過程で人員と予算措置についても鮮明化されており、図書費・設置費や、公立学校教職員の定数管理の問題、人的な手当ての問題などにより、実質的に学校図書館が機能しない形になっていく過程が描かれている。
「学習者が問題や課題を見つける」「調べる」際に、学習者が自ら調べる資料をいかに教師が準備するのかという現代に通底する話が、戦後初期に既に論点になっている。その際に、「教科書以外を教材にできること」が学校図書館への期待へと繋がった話や、教材として作成された資料集ではなく、調べるための参考資料が必要とされた話などが印象的だった。
個人的には、戦後の経験主義→系統主義の変化によって図書館活用の可能性が妨げられたとする話、それがアメリカの同時期のSchool Librarianの発展と異なるという話から、日米の「系統主義」の違いを実感する。アメリカの教育方法や考えを日本の教育風土に持ち込むことの困難さは様々に見られた(例:「教権」的な教員像や、教師の役割の無境界性)。
過去の事例紹介も豊富。大田区立田園調布小学校の事例には、アメリカの進歩主義教育っぽさを感じたが、学校図書館を機能させるのに、学校風土、校長のリーダーシップ、戦前期からの遺産、地域の他組織(組合含め)の影響等、様々な背景が絡むようだ。私としては、学校図書館と「まちづくり」の発想が関連しているように思えた。
図書館(利用)指導と読書指導の関係をどうみるか、という点も根深い論点の一つだった。全体として、学校図書館改革が、教科のあり方、教師の役割、教職員の関係性など多岐に及ぶこと、それゆえ学校改革としてトータルで考察し議論しないと上手くいかないことが分かる一冊になっている。