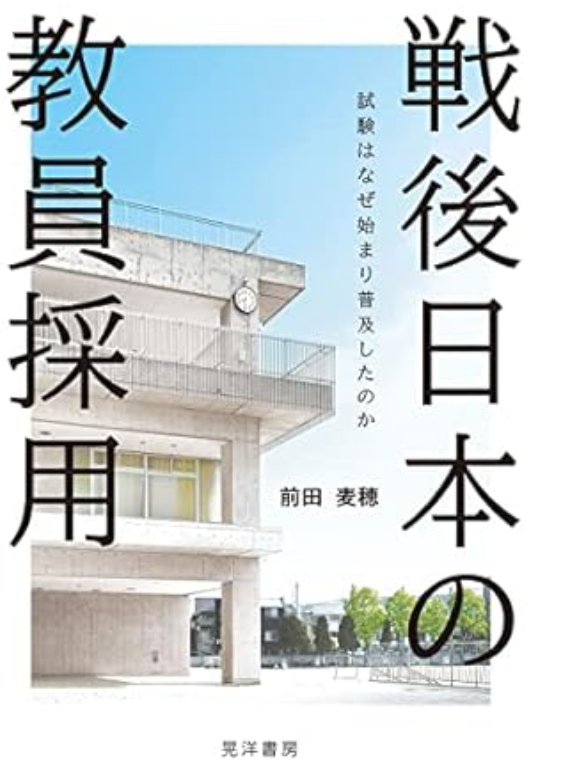
『戦後日本の教員採用』を読了。「教員採用試験」の語は今では当たり前のように使われるが、そもそもこのような試験が普及したのはいつで、その目的はなんだったのか。日頃頻繁に見聞きするこの語の過去を辿る本書を読んで、歴史的アプローチの醍醐味を感じた。勉強になった。
そもそも、日本各地へ試験方法(と法解釈)が普及する実態をたどる発想自体が、私には刺激的だった。当然ながら、普及実態は一様ではなく、トップダウンに一気に進むものでもない。各地の背景(社会経済的条件)を分析する各章の考察が面白い。戦後直後は、選考試験をしてなかったことも知らなかった。
戦後初期に教員が足りずに苦労する自治体。一気に教員志願者が急増し、何らかの選抜が不可避になる状況。選考の理念よりも教員志望者の量的・質的な変化にかなり影響を受けることがわかる。人数制限の方法と理屈に各地で悩んでいる。各地の国立大教育学部との関係が選考方法に密接に関連していた。
同時に自治体ごとの多様性の中から浮き彫りになる論点は多い。採用の需要供給関係は各地で異なる。都市部と地方の関係、大都市と郡部の県内格差、県教委と市教委の関係も顕在化。志望者数が増加する一方で、財政逼迫故に新卒が取りづらく、教委が年配教員の勇退を促し組合と対立する構造などは印象的。
全体を通して思うのは、志望者の増減という、志望者本人にはどうしようもない要因によって、志望者自身が振り回され続けていること(それは今も同じか)。何かもっと良い解決策はないのかとモヤモヤ。その他、本書が一貫して、「教育委員会法=地教行法の断絶説」の通説を問い直す姿勢が刺激的だった。