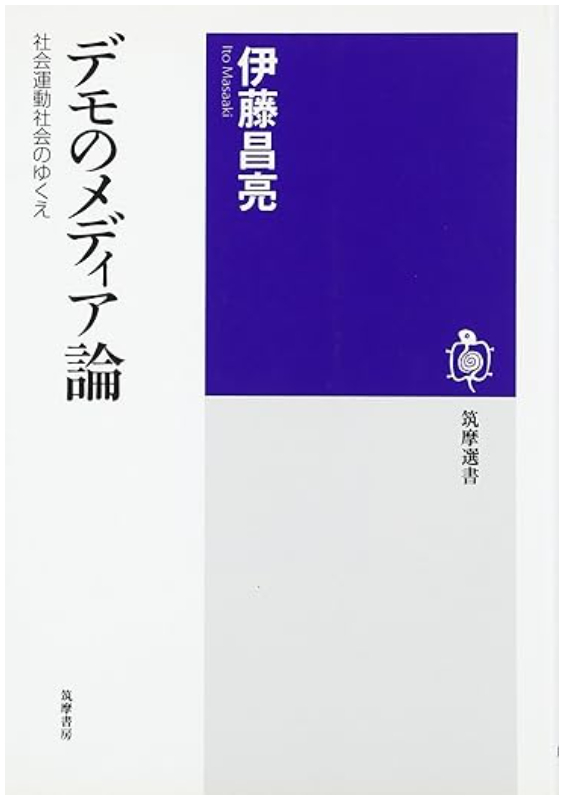
『デモのメディア論』を読了。「デモ」のイメージを何度か揺さぶられた。本書の前提として、2011年以後の反原発デモをはじめ、1960~70年代以来の高まりが起こっており、「社会運動社会」が到来していること、現代のデモが一般的なイメージとはやや異なることが指摘されてる。
具体例として、市民運動型のデモ、サウンドデモ型のデモの対比がされる。両系譜は今も存在し混在もしているが、後者がより現代的な傾向。両者の参加層や集団的アイデンティティの捉え等が大きく異なる。世界中で連鎖し合う社会運動の流れや、1960年代以降の社会運動の展開についても詳述されてる。
個人的には、本書の後半が熱かった。特に「オフ会としてのデモ」「潜在的な意味のネットワークの局面」の話は、私にとっての「デモに参加する」見方を大きく変えた。ソーシャルメディアを介した、意味のネットワークもデモや社会運動の一部(重要局面)とすれば、参加の定義も変わるのではないかとも。
加えて印象に残ったのは、社会運動社会が、(新しい)テロリズムや排外主義的な「憎悪する運動」をも生みだし、危うさを備えていること。著者はその危うさや困難さも理解しつつ、困難な道を進むしかないともいう。これは、市民を育てる教育にも、重なる部分がある話だと感じた。