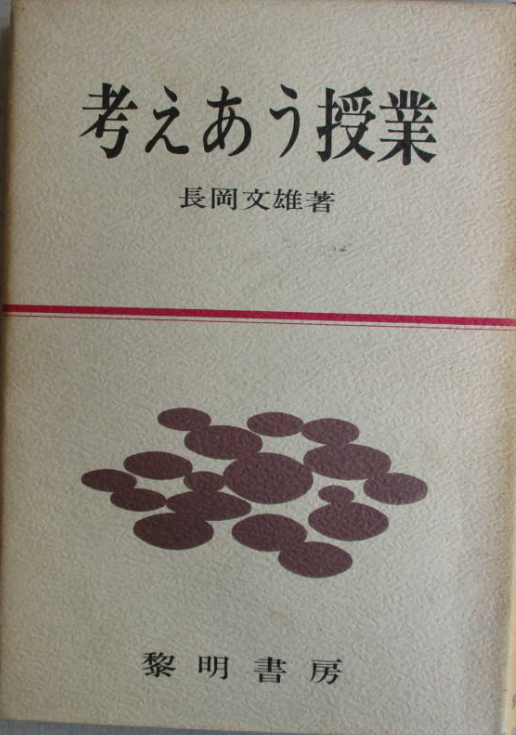
長岡文雄『考えあう授業』を読了。著者は、児童一人一人の個性的な学びや考えを尊重することを奨励するが、それでいて教員側の指導性や教材研究の重要性も強調する。その両者をどう両立するかという点に関するヒントが、本書に書かれているように感じた。
著者は、子どものつぶやきや作文を観察し、一人一人の思考体制を読み取る。そしてその上で、その思考体制をゆさぶるような「一人一人の子どもを根っこから掘り起こしていく」授業を実践する。児童の気づきや意見のズレに注目しつつ、児童の関心が「共通問題」へと熟していく過程を観察するのだ。
特に印象に残ったのは二点。授業の「生きた流れ」を重視していて、授業とは「二度とやり直しのできない交響楽の演奏のようなもの」と表現している。もちろん教師は計画を立て準備をするが、教室空間で起きる児童同士の即興的なやりとりから授業を展開していく様はまさにそんな印象を持った。
もう一点は教材研究。児童の思考体制を強く重視しているので、教材研究は目の前の「子どもを通して」行うべきと何度も強調する。そして児童の作文をもっと読んでおけば授業展開も変わっただろう、と自身で反省するくらい、児童の声を教材として使おうとする意識に満ちているのが伝わってきた。
考えあう授業には、「ゆとり」「幅」「自然さ」「間」が重要であるとする(pp.38-39.)。これらの主張には、ある意味で一部の授業研究、教育学研究を批判する意図もあったのかもしれない。実践者だからこそできる教育研究のあり方を追究されている熱量が随所に散りばめられているように感じた。