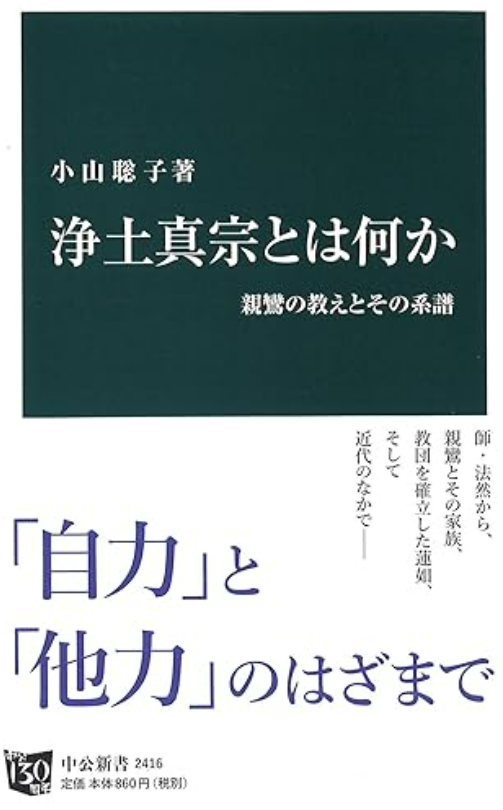
小山聡子『浄土真宗とは何か』を読了。自己の努力による修行ではなく、念仏を唱え、他力による極楽往生の可能性を説いた親鸞。その本人や弟子、後継者たちの思想を分析して、弟子はもとより親鸞本人も「他力」のみに振り切って考えてはいなかったことを論じている。
呪術や神秘的、多神教的発想が当たり前だった中世社会において、親鸞自身も悩み論理に揺らぎがあるし、弟子や関係者も、親鸞の考えに理解を示しつつも、当時の時代の価値観にも合わせるという、ある種のダブルスタンダードというか、折り合いをつけながらやっていた部分もあるようだ。
印象に残ったのは、蓮如が影響力を拡大する中で、本人は理論的理解ができていたとしても、皆に分かりやすいように教理を簡易化して伝えたという点。弟子にも全然、教理の本質部分がが伝わらないと蓮如が嘆いている点も同じくだった。組織の拡大と、教理の深化は必ずしも一致しないということか。
教育に置き換えて考えると、理論・思想も時代や社会的な文脈と合わせて考える必要を再認識する。革新的な思想も、他者に理解してもらい影響力を持つためには、時に妥協/折り合いも必要であり、そのために簡略的な説明も必要であり、でも本質は失ってはいけない・・という葛藤があるのがよく分かった。