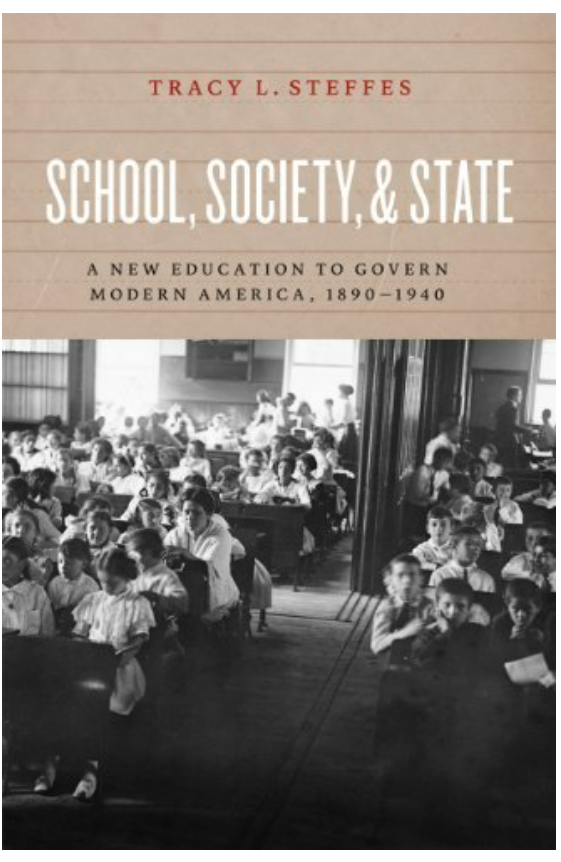
目次は以下の通りです。
– Introduction
– Urban School Reform Professionalization and the Science of Education
– The Rural School Problem and the Complexities of National Reform
– Redefining State Responsibility in Education
– Public Interest and Parental Authority in the Compulsory School
– Curriculum Reform and the Aims of Education in a Democracy
– School Society and State
非常に面白かったです。20世紀前半の学校教育史を紐解きながら、その歴史を、(今まで見落とされがちであった)州権力の拡大の歴史として、全米規模でのシステムとしての地方分権化の歴史として、さらにアメリカ的な福祉国家の形を作った歴史としても捉えています。
私の問題関心から見て、本書の内容について、
印象に残った点を三点メモしておきます。
一点は、20世紀前半の米国教育史を「州権力の拡大」という文脈からとらえ直している点です。
代表的な教育史研究が注目するのは、多くは都市部や代表的な学校になりやすいですが、本書はそのような大都市に注目しがちな教育史研究を批判し、各州の権力成立過程として描いています。
20世紀前半のアメリカでは、まだ田舎の学校や複式学級なども沢山あったわけで、そのような中で、なぜ全米規模での教育改革が産まれていったのかという点に注目しています。
実際、各州の権力が拡大し、州単位が相互に影響を与え合いながら、教育行政の専門職化や教職の資格化などが進んでいったこと、それが全米レベルでの共通性を生んだことなどが示されています。
その論証の過程で、本書は田舎の学校や教育行政に視点を焦点をあてていきます。教育長の配置の議論や、学校統廃合に伴う施設・人員の整備の調整などをも軸にしつつ、緩やかに州による教育のコントロールが進んでいったとされます。
二点目は、州と学区や地域の関係についてです。
州権力の拡大が起こったとしても、トップダウン的に改革が進んだわけではなく、地域のプライド(ローカルプライド)や主体性を尊重しながら、細かな規制でしばらずに、自主的な取り組みや工夫を促す点が特徴として説明されています。
実際、多くの州では、20世紀前半に州教育局の規模(人員、責任)が拡大したのですが、一方で学区の力も尊重しようとした。そのため、州権力は細かな規制はせずに、緩やかな州全体でコントロールをしようとした。具体的には、資金援助、教科書の採択、スコアカードなどによる標準化、大学進学をめぐるアクレディテーション、学校調査、州内の競争意識を高めるランキング化など。これらの仕組みを徐々に作り上げながら、州全体の共通性や統一性を緩やかに作っていった。
また、メンターや相談役としての地方の教育長、スーパーバイザーの権限や人員が拡大していったのもこの時期でした。
一方で、各地域で行う改革内容については、学校や地域の主体性を喚起するために、細かい規制では縛らない。結果として、学区や地域の自主的な行動を促す工夫を様々に展開していく。草の根の団体も様々に展開された。これによって、田舎の教育を底上げしつつ、都市部や富裕地域を縛らないことができた。
ただ、ローカルプライドを重視した結果、州の強制的な介入による格差是正などはなされなかったので、不平等や格差は温存される傾向にあった。
これらの州と地域・学区の関係は、20世紀前半の教育改革が、トップダウン的なものとボトムアップ的なものの相互によって起こったことを示しています。
三点目は、20世紀前半の米国教育史をアメリカ的な福祉国家の形を作った歴史として示していることです。
一般に、米国は福祉国家としては脆弱と言われますが、そういう議論では学校教育が果たしている社会福祉的な機能を見落としている部分がある、と本書は指摘しています。一例として、米国が世界で初めてハイスクールの大衆化を遂げた理由をどう説明するかと本書の導入で問題提起もされています。
20世紀前半の学校教育は、子ども達を「保護」しようとする方向に舵が切られました。
例えば、児童労働法や義務教育法の制定や強化、親の教育権よりも州の教育権を高く捉える流れ、非行対策、職業指導の強化、公衆衛生、健康管理の文脈でのワクチン接種義務化の流れなどもこの一環に含まれます。広くは、公民科教育、シティズンシップ教育の議論もここに含まれます。
また、民主主義と産業資本主義を接続するために、学校教育の役割が期待された結果、カリキュラムが分化し、生徒のニーズや関心に合わせて多様な教育内容を受けられるように変化していった(いわゆるトラッキング化)。こういった個別化の流れと、職業指導の親和性は高い。
ただ一方で、これらの保護的な政策は、基本的には、「規制」としての性格が弱く、機会を提供していく性格、言い換えれば本人の選択にゆだねる性格が強かった。結果として、強硬な格差是正や教育投資策は取られないので、(構造的な格差を含みながら)様々なリソースの少ない地域や社会集団は、結果として放置された。この点から、ヨーロッパ的な社会福祉的文脈の学校教育史との差異が強調されています。
要するに、ハイスクールを大衆化した光の部分と、最終的には個人の自己責任に委ねる影の部分が、アメリカの福祉国家像を体現している、ということなのだと私は理解しました。(勿論、単純に現代と比較するのではなく、同時期の他国との比較をしてみる必要がありますが。)
大まかな論点としては以上です。
これまでの教育史に「州」の存在を意識的に加えることで、トップダウンでもボトムアップでもない双方向的な動きを捉え、都市部以外の教育状況をも説明しようとしている点は刺激的でした。
また福祉国家の議論は、教育史を広く扱い、様々な文脈と関連付けて論じているように思いました。
勉強になりました。