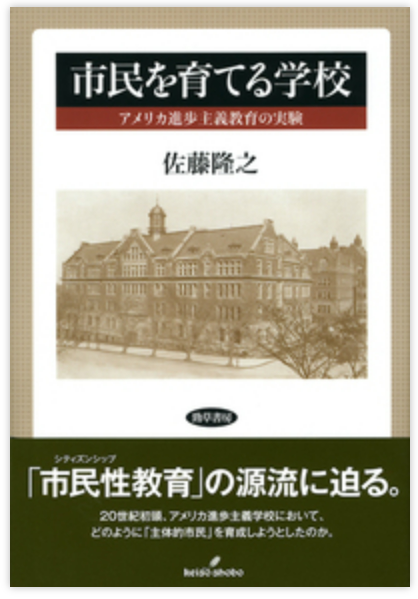
目次は以下の通りです。
はしがき
序章 アメリカ進歩主義教育における市民育成の実験
第一章 「主体的市民」を育てる――ホーレスマン初等部における実験
第二章 ホーレスマン・スクールの教育環境――市民育成の舞台
第三章 市民性プロジェクトの立案と実践――ロイ・W・ハッチの市民性訓練論(1)
第四章 市民性プロジェクトの理念と過程――ロイ・W・ハッチの市民性訓練論(2)
第五章 市民性の測定と指導――クララ・F・チャセルを中心とする市民性尺度の開発
第六章 進歩主義の市民性教育論議――実験の背景
終章 進歩主義教育のなかの「市民を育てる学校」――自発性・付随性‐指導性問題と「よい市民性」
久しぶりに読み直して、良い本だなあと実感しています。
米国ニューヨークに位置するコロンビアティーチャーズカレッジの附属校であるホーレスマン・スクールの授業、学校づくりに注目し、学校で市民育成をする様子を詳細に描き出しています。
「ホーレスマン・スクールは、ティーチャーズ・カレッジで、幼稚園の教師やデューイからの協力も得られた点において、他の進歩主義学校とは一線を画している。」(p.3.)とされるように、理論と実践の関連性を随所に感じられる点も示唆が多いです。
印象に残った点を三点メモしておきます。
一点目
学校全体での市民育成という点がイメージできる点です。教科でも、学校全体でも、様々な活動を関連付けていることが分かります。
このようにホーレスマン・スクールでは、教室の生活を全面的に生かしながら、教育課程の内外で、様々な方法を要して多面的に市民を育成しようとした。それは、教科の枠、学校と社会、学年や学校種などを超えて学校をあげて行われた、総合的で統合的な市民育成であった。
p.10.
このような話は、「プロジェクト・メソッドを適用した市民育成を構想したハッチにとっても、講堂は重要な方法の一つであった。」(p.109.)と言われるように、校舎や学校環境をフルに生かした教育構想を練っていたことが分かります。
二点目
ホーレスマンスクールでは、児童生徒の主体性を大切にしているのですが、その際に環境の設計にかなり力を入れています。
そのようなねらいのもとで推進されたホーレスマン初等教育研究の主眼は、「環境が刺激する」教育の実現に置かれていたともいえる。教師が教え、それを子どもが学ぶというのではなく、「環境」に「刺激」されて子どもが活動を開始し、展開できるようにする。それにより主体性を発揮させ、活動を通して知識、技能、態度などを身につけるようにする。
727272
この環境設定の議論は、生徒主導の活動を重視しつつ、その自然な願望を喚起させるための「舞台設定」なる環境の設定に配慮している点(p.147.)にも随所に感じられます。学校環境のデザインの話ともつながり、同時に戦前の木下竹次の「環境整理」の話が頭をかすめました。
三点目
市民性の育成を「付随的に」行っている点です。この付随学習というのがホーレスマンスクールや特に取り上げられるハッチの授業論の一番の中核にあるように私は読みました。
と同時に、この市民性教育の「付随性」を認めることで、本書で示される実践の幅がひろがり、面白みが増しているように思いました。
この三類型をみると、市民性プロジェクトは厳密に定義されているわけではなく、様々な取り組みが幅広く取り上げられている。そのような包括的な理解が示すように、市民性プロジェクトは学校生活全体を通して行われた。タイプAにおいては教育課程外で、タイプCにおいては教育課程内で意図的計画的に実践された。タイプBでは、学校や教室での生活を通して、付随的事後的に展開された。・・・(中略:斉藤)・・・ホーレスマン・スクールでめざされた「主体的市民」育成においてとりわけ重要になるのは、「市民性の付随物」を原理としていたことからして、タイプBの「付随的プロジェクト」である。市民連盟と少年クラブや通常の授業においても付随的な学びは展開されるから、タイプAとCもタイプBに包括されることになる。
p.135.
市民性の育成の目標を掲げてダイレクトにその目標達成を狙うというよりも、市民性の育成に付随的に寄与すること、いいかえれば副次的な効果を期待するという発想ゆえに、様々な授業スタイルと柔軟にマッチングが履かれていたのだろうと感じました。
四点目
教科の位置づけについてです。
先の付随的な学習の理論が組み込まれることで、教科の学習が否定されることなく、活かされている点です。
この際に、ハッチがいわゆる年代史的な歴史学習を行っている点などが非常に象徴的だなと思います。
そこにみるように、従来の教科を中心とする教授法が否定されたわけでもなかった。ハッチ自身、労働プロジェクトにおいては従来通りの年代法を用いて、18世紀の歴史や、19世紀に入ってからのヨーロッパの地理を教えている。ハッチはまた、市民性尺度を市民性プロジェクトに転換しようとする一方で、逆に市民性プロジェクトの評価法を考案することで市民性尺度に接近してもいた。所定の市民性の徳目を教えて評価する場合もあったのである。
p.293.
こういう射程で捉えたとき、いわゆるAHA7人委員会のような歴史教育と、1916年のNEAの社会科報告書の歴史教育のあり方に根本的なずれがない、とみる見方も可能であるようにも感じました。
また、この種の教科との関係性の議論は、市民育成における教師の指導性の議論とも関係しているように私は理解しました。教科横断的な授業や、児童生徒の興味に応じた自主活動も認めつつも、教師が主導する授業場面も同時に重視していた、ということかと感じます。
このような解釈を補助線として、本書で考察してきた市民育成の実験を総合的にみると、それは、プロジェクト・メソッドに従って「児童生徒が決定するプロジェクト」をめざしながらも、実態においては「教師が先導し、児童生徒が推進するプロジェクト」に近かったように思われる。すなわち、ペコーレの言葉を借りれば、実験に実践された市民性プロジェクトは、子ども達による「自己決定プロジェクト」ではなく、教師に導かれた「自己推進プロジェクト」であったのではないだろうか。
p.291.
その他、20世紀前半の市民性を保守性と革新性の観点から多角的に考察している第6章なども読みごたえがあります。
また、ハッチとキルパトリックの認識のずれや、市民性の評価の目的や方法をめぐる論点なども、面白いです。
現代の市民性教育に関わるような授業方法や思想的な葛藤の具体例を、100年前の実践から示す本書の魅力は大きなものがあります。