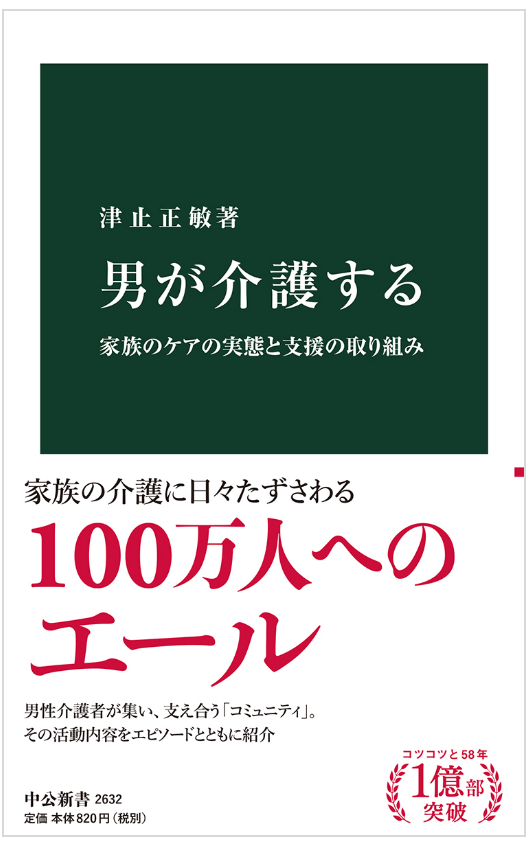
介護に携わる男性の生活の実態や関係者の思い、そこから見える日本社会の今後の展望などが描かれています。
論点は制度面から歴史、他国の状況など、多岐にわたっているのですが、感情移入しそうになるようなエピソードが豊富に語られており、読みやすいです。思わず目頭が熱くなる場面が何度もありました。
私自身、介護についてこれまでじっくりと考えてこなかったことを恥じつつ、同時に様々な気付きがありました。
いくつかメモを残します。
一点目
介護が、私たちが人間であるということ、人間がケアし、ケアされるべき存在であるということを、象徴することなのだと実感できる点です。
介護は、この社会にとって必要悪やお荷物かのような扱いを受けている。人間社会のデザインからはあってはならないことと、傍流に追いやられ、周辺化された特殊な世界のことではないかという理解に依拠すれば、私たちのケア・コミュニティにもそうした全くのネガティブな評価が付きまとうであろう。そうではなく、樋口恵子さんが男性介護者と支援者の全国ネットワークの発会式で寄せた「介護することは人間の証明です」というメッセージのような人間社会の普遍性ともいうべきものであれば、ケア・コミュニティこそが人間社会の最もあるべき普遍的な姿を何よりも早く先取りして具現化したものとして評価されてもいいのではないか、とも思う。
pp.195-196.
介護のイメージを捉え直すことで、社会全体をケアのある社会として捉え直すことができるのではないかと、認識することが出来ました。むしろ、そこに潜むネガティブなイメージを変革していくプロセスにこそ、意味があるようにも感じます。
この話は、最後に紹介されていた当事者研究で有名な熊谷晋一郎さんの「周囲の力を借りながら生きていくことを「自立」とする」という発想とも接点は濃いと思いますし、誰もが変化する自分を受け入れ、安心して暮らせる人生を展望するためにも、大切な視点だと感じました。
二点目
介護に対する男性の関与の比率が、他の家事・育児と大きく異なっている点も印象に残りました。
もちろん、家事・育児の実態も絶えず改善されていくべきだとは思うのですが、まさに、夫婦や家族の頼る・頼られるの関係を捉え直す意味でも、介護の問題は示唆に富むように思います。
育児休業該当者のうち休業取得している女性80%超に比して男性はいまだ10%にも満たないというあまりにも大きな男女差に比べ、介護分野での性差は驚くほど縮減していた。主たる介護者の男女比では女性2に対し男性1ということや育児に比して圧倒的に性差の少ない介護休業の取得率。こうしてみると家族の介護を二担う男性こそ支援の対象とする社会モデルにふさわしいのではないか、と考えたからだ。
pp.12-13.
三点目
ここがまだ私には理解しきれていない点でもあり、同時に本書にとってとても重要な問題提起だと思うのですが、介護が大変でありつつも、そこに希望を感じられる瞬間があるという点についてです。
これは先のケアの関係とも関連し、いずれか片方が一方的に頼られたりするわけではないという、双方向的な関係性を感じさせるものでした。とはいえ、一つ一つの介護のエピソードが非常に重厚感がある内容なので、私自身が消化するのに時間がかかってはいます。でも重要な論点だとは実感しています。
介護はつらくて大変だということは、言うまでも厳然たる事実に違いない。ただ、留意したいのは、私たちの取材に対応し介護体験記を記した多くの介護者が異口同音に「でも、そればかりでもない」と発したことだ。介護はささやかなりとも希望にも喜びにも浸れるような、直面して初めてその価値に気が付く生活行為でもあるということだ。この社会の主流となっている、介護を排除してこそ成り立つような暮らしと働き方への異議申し立てと言えよう。本書が提起しようとしている「介護のある暮らしを社会の標準に」という主張はこうした「つらくて大変、でもそればかりではない」という介護者の両価的感情との出会いから生まれたものだ。
p. 4.
社会保障の問題が、ケアや、共感など多様な論点へと広がっていくことを感じられる本となっている気がしました。
勉強になりました。