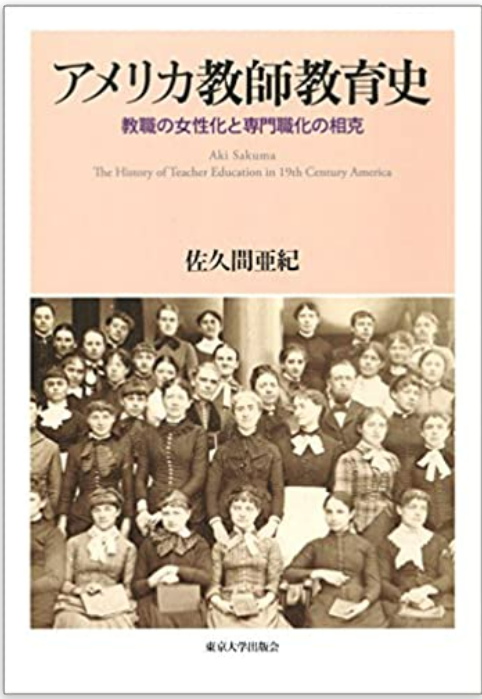
AmazonのWeb
目次は以下の通りです。
まえがき いまなぜ,アメリカの教師教育史か
序章 教師教育という視座
第I部 州立師範学校前史
第一章 教師教育理論の導入と展開――男性指導者による教職の専門職化言説
第二章 女性教師像の成立――エマ・ウィラードの「共和国の母」としての教師像
第三章 女性のための専門職像を求めて――キャサリン・ビーチャーの専門職としての教師像
第四章 女性による教職専門職化批判――メアリー・ライアンの聖職者としての教師像
第Ⅱ部 州立師範学校の実際
第五章 初期州立師範学校の実際――背負わされた宿命
第六章 校長補助教師と呼ばれた女性たち――イレクタ・ウォルトンの葛藤
第七章 女性教師の日常世界――日記と手紙から
第Ⅲ部 州立師範学校の普及と変容
第八章 州立師範学校の普及と変容――教育需要の拡大と序列化競争
第九章 女性校長の出現とその意味――アニー・ジョンソンとエレン・ハイドの思想と実践
第十章 専門的養成をめぐるカリキュラム論争――ジュリア・キングの思想と実践
終 章 教職の女性化と専門職化の相克
あとがき
本書では、「19世紀米国における教師教育の歴史を、ジェンダーの視点から再検討する」とされています。
より具体的な方法としては、以下のように述べられています。
州立師範学校の設立前・初期・発展期の各時期に、教師の養成に携わった七名の女性の思想と実践の分析を通して、19世紀米国における教職の女性かと専門職化の史的展開を明らかにすることを本書の課題とする。
p.1.
このように本書では7人の女性の足跡をたどっていくのですが、一人一人の考察に際して、歴史研究としての方法論の緻密さが印象に強烈に残りました。日記や手紙などの史料が多数使用されているように思いました。日記の内容などは一人一人の女性の感情を表現した内容も多く、読みごたえがあります。
全体として、教職という職業が女性化していったことがよく分かります。
19世紀初頭までは主に男性の職業であったとされる教職。それが、ウィラードをはじめとした主唱者たちが、女性の社会的活動としての教職の役割を正当化していく。その後、初等学校を中心に女性の割合が一気に増えていく。7名の足跡をたどる中で、このプロセスが自然と理解できます。
第3部で明らかにしたように、州立師範学校は女子校として創設され、19世紀半ばにはすでに学生の大半が女性によって占められるようになっていた。女子学生の割合は教職の女性化の進展に伴って全米各地で上昇し、19世紀後半には共学の州立師範学校においても、学生の6割から9割は女性によって占められるようになっていた。
p.288.
そのうえで本書では、
「19世紀米国において女性が教師教育に少なからぬ役割を果たしていた事実を明らかにしてきた」こと、「従来は存在しないものとされてきた女性教師たちが、そこには確かに存在していた」こと(p.429)などをまとめたうえで、
「米国の近代学校の教職史を踏まえれば、ジェンダーの視点を欠落させた教職論はほとんど無意味であることが明らかである」(p.432.)と述べています。
印象に残った点をメモしておきます。
一点目は、州立師範学校が背負う、他の教育機関との位置づけや社会的役割の期待が、登場する7人の女性を翻弄していく点です。7人の女性が求めて得たというよりも、まさに翻弄という感じです。
その背景には、初期の州立師範学校が「すなわち初等教育を担う教師を要請することを目的として成立したこと」により、「その教育機関としての社会的地位を、小学校教師という職業の社会的地位の低さと密接に関連付けられる宿命を負ったこと」(p.202.)とも深くかかわっているとは思います。
とりわけ、19世紀後半に入ってからの州立師範学校の「四重の課題」というのがまさに強烈でした。
つまり州立師範学校は、四重の課題に直面していた。一方では、研究大学を頂点とする高等教育機関の序列化が進む中で、以下に大学としての性格を整えていくかが課題となっていた。学位授与研の獲得や大学昇格化は、教師養成のためにも、すなわち優秀な男子学生を獲得するためにも、避けては通れない問題だった。しかし他方で、州立師範学校は、本来の設立目的である教師養成をいかに維持するかという課題にも直面していた。州立師範大学が大学としての性格を強めると、既存の高等教育機関と競合しなければならず、独自の存在意義を示す必要に迫られるからである。さらにその際、中等教育段階の教師の養成に特化すれば、すでにその養成をおこなっている大学や総合大学との競合関係にさらされ、教育機関としての存続自体が危ぶまれる事態になる。しかし競合を避けて独自性を出すために初等教育段階の養成機能に特化すれば、大学程度の教育水準をもった志願者の確保が事実上困難となり、教師養成期間としては存続できても大学には昇格できないというジレンマ状況におかれていたのである。
pp.303-304.
二点目は、登場する女性たちが、教職を目指すうえで学問教育を重視して姿勢が類似していたことです。
逆に、「実技訓練ばかりを重視する教師養成カリキュラムは、ハイドにとって受け入れがたいものであった。」(p.354)「キングは、教師教育の前提として、学生自身が科学的探究としての学習を経験していること、すなわち学問や学習の意義を体得している必要があると考えた」(p.395.)という指摘にもあるように、学問を体得していることが重要とされています。以下の整理は読んでいて腑に落ちる場面でした。
多くの州立師範学校においては、教育技術の教育を重視する教養教育か、教科内容知識の教育を重視する学問的教育か、という二項対立の論争が主流だった。この当時の状況のなかで、ハイドやキングが教科知識と教授技術に加え、それら知識や技術の基底にある思想や哲学を基に、個別の教室の状況に即して試行する力量の重要性を指摘していたことは、20世紀末にドナルド・ショーンらの研究によって引き起こされた教師教育のパラダム転換を予見させるものとして、注目に値する。
p.425.
三点目は、教師養成機関の問題は、その機関内や卒業生の質向上といった点では解決できないことが多いという点です。
教師の能力の向上は、教師養成機関のカリキュラム改善や高度化によってのみ達成しうるものではなく、教職の労働条件や需給関係など、教職をめぐる社会的状況への対処や、教師養成機関を一方的に非難するばかりの世論への対処も、重要な要素となる。
p.441.
この点は、カリキュラム研究をする自分自身も弱い視点だなと痛感しており、同時にその必要性を強く感じました。
全体を通して「分厚い研究」だなと感じる瞬間がとても多かったです。
勉強になりました。